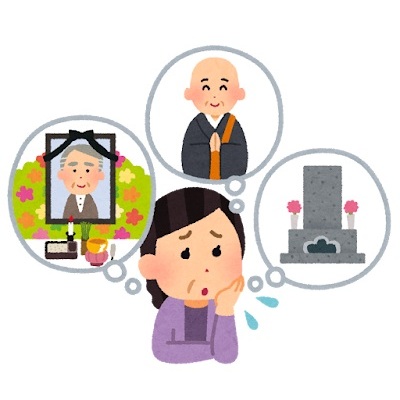光回線の乗換勧誘電話でトラブルに
- 2025年9月29日
- main-admin
ある日突然、Xさん(ご相談者)の携帯電話に電話が掛かってきました。「当社は大手通信会社N社の提携会社(プロバイダーS社)の営業の者(女性)です。光回線とプロバイダをセットで乗り換えると、現在の大手通信会社よりも料金が確実 …
クーリング・オフ
- 2025年9月15日
- main-admin
クーリング・オフはどのような制度? 誰でも一度は聞き覚えのある言葉だと思います。 Cooling Off すなわち、冷静に考えて契約から離れる、という意味だそうです。クーリング・オフとは、訪問販売や電話による勧誘販売など …
借入の保証人になるとき
- 2025年9月6日
- main-admin
個人の方が、個人事業主や事業性法人等の事業性借入の連帯保証人になる場合には、借入金の契約を締結する前に、公証役場での手続きが必要です。ただし、保証人(予定)の方が個人事業主の配偶者である場合や、事業法人の役員及び議決権の …
相続手続について
- 2025年8月13日
- main-admin
「相続」とは、人が死亡したときに、その人の財産上の地位(権利、義務)を次世代に伝達し、誰にどのような形・内容で承継させるかということをいいます。人(自然人)は寿命があり、誰にもかならず相続は発生しますが、その日は突然に訪 …
戸籍とコンピュータ化
- 2025年8月10日
- main-admin
今更ながら「戸籍とは何で、住民票基本台帳があるのに何故存在するの?」という疑問を持つこともあると思います。何のためにという意味では、次の2つの意味があります。1.日本人としての存在証明2.親族関係が証明できる 戸籍制度が …
戸籍謄本等の広域交付制度
- 2025年8月1日
- main-admin
戸籍とは 明治時代(明治5年)に初めて戸籍ができました。江戸時代の人別帳や宗門帳を踏襲した家の登録制度であり、戸主(家の長)を筆頭者として、その家族を記載したものが「戸籍」です。 戸籍がある場所を本籍といい、戸籍は各市区 …
相続土地国庫帰属制度
- 2025年7月31日
- main-admin
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に限り、国に引き取ってもらう制度です。 思えば、昭和40年代の日本列島改造論や昭和50年代の別荘ブームなど、過去に …
現役世代の保険料負担は大変!
- 2025年7月30日
- main-admin
この投稿をするに至ったのは、「そういえば、ボーナスから健康保険料が徴収されるようになったのは、いつからだったのか?」という漠然とした記憶があったから。それに加えて、先の参議院議員選挙で、ある野党の党首が「社会保険料負担が …
遺言書の検認
- 2025年7月28日
- main-admin
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません(民法1004条)。なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されて …
遺言書保管制度について
- 2025年7月25日
- main-admin
自筆証書遺言書は、自ら単独で手軽に、かつ秘密で作成できるなど良いところがあります。でも、死亡後に相続人が発見できない可能性、又は一部改ざんされる恐れがあったり、或いは適切な保管場所が無い等の課題もあります。その課題を解決 …