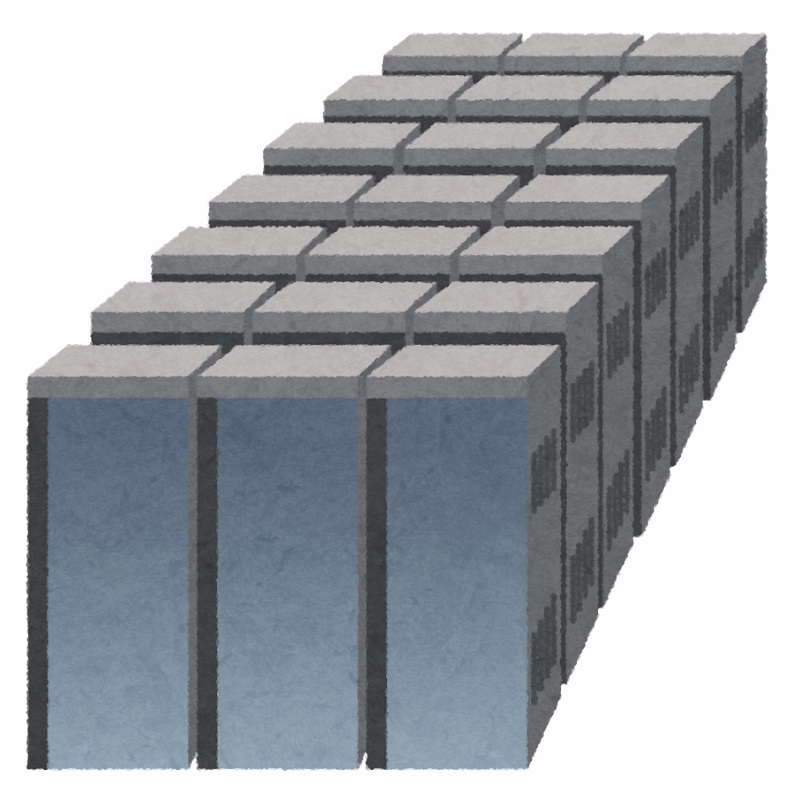今更ながら「戸籍とは何で、住民票基本台帳があるのに何故存在するの?」という疑問を持つこともあると思います。何のためにという意味では、次の2つの意味があります。
1.日本人としての存在証明
2.親族関係が証明できる
戸籍制度ができたのは明治5年(1872年)のことで、申(さる)年であったため、壬申(じんしん)戸籍といいます。その後、数度の改正を経て現在に至っています。
例えば、昭和22年戸籍法改正では、戸籍の基本単位が「家」から「夫婦」に変わり、「戸主」から「筆頭者」に変わりました。昭和改製原戸籍は改製前の古い様式のため、「家」を基本単位として「戸主」が記載されています。
平成6年の同法改正では、戸籍事務はコンピュータで記録・処理できるようになり、「B4サイズ縦書き」から「A4サイズの横書き」に変わりました。ただし、平成改製原戸籍は改製前の古い様式のため、縦書きの文章形式で記載されています。このように戸籍制度そのものの変更もあれば、コンピュータ化による改製(データの載せ替え)で一部記載されなくなった内容(例:改製前に除籍された人の情報、改製前になされた「認知」「養子縁組」「離婚」)もあります。
話が横道に反れましたが、いまの戸籍は、夫婦とその子供(未婚)を単位として、新しい戸籍が編成されます。その子供が婚姻をすると夫婦一緒で本籍地を定めることになります。
戸籍の所在地が「本籍(地)」となります。日本人である人は、必ず本籍地があります。このため、日本人としての存在を証明することができるわけです。なお、婚姻により本籍地を定めるとき、その場所は全国どこでも自由に定めることができます。しかし、戸籍を管理するのは本籍地の市区町村役場になるので、住民基本台帳の住所(居所)と異なっていても構いませんが、一緒の方が望ましいといえます。
戸籍が編成されると、出生や婚姻、離婚や死亡等の身分関係が書かれていきます。つまり、いろいろな届出の履歴が記録されていく、公文書としての役割があります。これらの身分事項をたどることにより、親族関係も証明できることになります。
(参考)
戸籍の記載事項(戸籍法13条)
1.氏名
2.出生の年月日
3.戸籍に入った原因及び年月日
4.実父母の氏名および実父母との続柄
5.養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
6.夫婦については夫又は妻である旨
7.他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
8.その他法務省令で定める事項
平成16年11月1日より、戸籍事務がコンピュータ化され、戸籍事務はコンピュータで保存・管理されています。ただし、移行時点で効力のない過去の届出の履歴は移行していないことから、相続手続等で「親族関係」を証明するための証明書として戸籍をそろえるときは、どうしても、コンピュータ化される前の紙の証明書を集める必要に迫られます。
令和6年3月1日施行された「戸籍証明書等の広域交付制度」は、法務省管理の「戸籍情報連携システム」により、各市区町村役場の戸籍を管理するシステムサーバーと連携した戸籍情報を、非本籍地である市区町村役場において、本人が申請することで、戸籍証明書等を入手できる画期的なシステム及び制度です。
利用者としては大変ありがたいことですが、システム運用を担っている方々の責任とご苦労は計り知れないものがあると思います。